こんにちわ。施設介護士ですが、4ヶ月間の男性育休を取得しているたまいちです。
2025年に第一子が誕生し、うちの介護施設では初めてとなる男性育休を取得しています。
男性育休は、赤ちゃんと過ごす貴重な時間を確保できる素晴らしい制度です。しかしながら実際に取得する上では、大きな壁が存在しました。
この記事では、僕が経験した「男性育休のリアル」を赤裸々にお伝えします。メリットやポジティブな部分だけでなく、職場異動宣告や上司からの圧力といったネガティブな体験まで包み隠さず書いていきます。
これから男性育休を考えているパパの参考になれば幸いです。
過去に前例の無い 介護士の男性育休の取得

介護業界で働く僕にとって、現場は常に人手不足。長期の休みを取るなんて到底無理だと思っていました。
ただ僕は2024年にガンになった経験から、家族との時間をとても大切に考えていました。
「この子の成長を妻と一緒に見届けたい」
「できるだけそばにいて、育児の大変さも喜びも分かち合いたい」
そう思ったからこそ、育児休業を取る決意をしたのです。
とはいえ、僕が働いている介護施設では、これまでに男性育休を取得した人はいませんでした。
介護士として14年目になりますが、今までに男性育休を取得したという介護士の話を耳にしたことすらありません。
介護士の男性育休のハードルが高いこともわかっていましたが、どうしても育休を取得したい為、施設長に相談しました。
男性育休申請の流れ
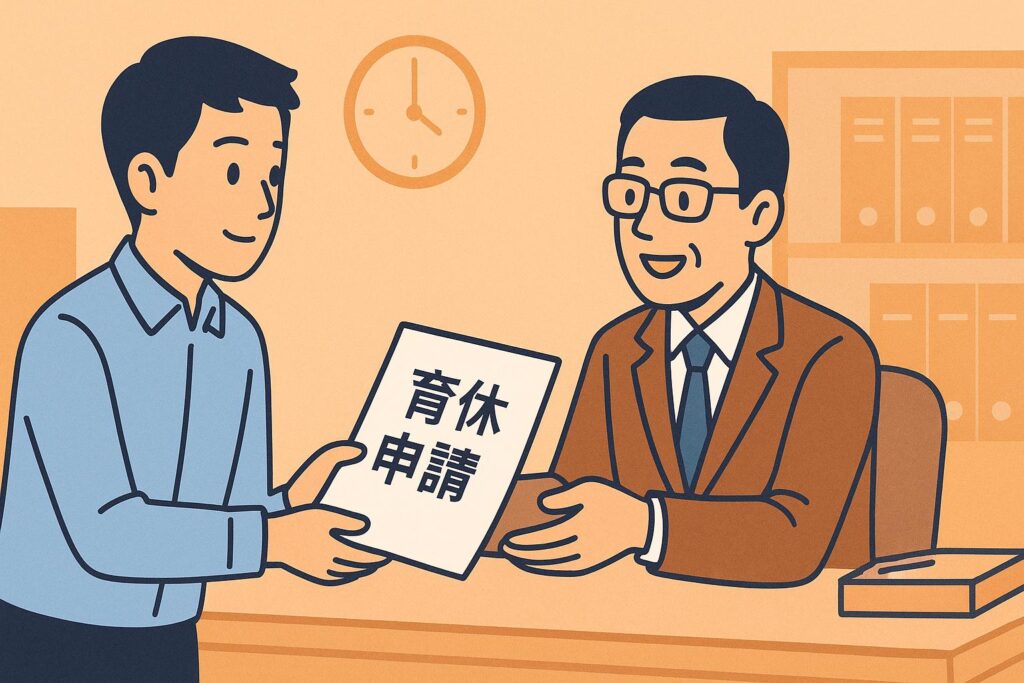
施設長に最初に相談した時の反応
正直、男性育休の前例が会社にないということ、僕はフロアリーダーでもあった為、育休を取ると現場が困ることはよくわかっていました。
ですが、施設長に「育児休業を取りたい」と伝えたとき、意外にも前向きな言葉が返ってきました。
「いいよいいよ!そういう時代だもんね!取ってくれていいよ!」
この反応を聞いて心の底からホッとしました。
会社としても僕のガンを経験している背景や時代的な育休推進の流れを理解してくれているのだと、その時は思ったんです。
上司との話し合いと申請の承認
直属の上司にあたる介護主任とも話し合いを行い、「4ヶ月間程度なら大丈夫」との返事をもらえました。
その後、細かい日程を相談し、事務所に正式に育休を申請したところすんなりと承認。
希望通りの「〇月〇日から育児休業を取得して良いですよ」という内容の書面も受け取り、ここまでは何の問題もなく進みました。
突然の異動宣告

ところが、事態は急変しました。
育休申請が通った後の とある日、施設長に呼び出され、こう告げられたのです。
「育休後少ししたら異動ね。移動先は〇〇(片道2時間かかる勤務地)だよ」
その一言に頭が真っ白になりました。片道2時間かかる勤務地??
子どもが生まれたばかりで、どう考えても育児と仕事を両立できる環境ではありませんでした。
僕は現状を正直に伝え、遠方への異動の撤回を求めました。
「異動自体は問題ないですが、その場所だと片道2時間の通勤時間がかかります。0歳の子どもを育てながら働くのは難しい。異動したら結局辞めることになってしまう。別の部署への異動なり、考え直していただけませんか?」
しかし、施設長の返事は冷たく突き放すものでした。
「個別の事情については聞く気ないから」
「もう異動先の施設長とも話してあるから」
僕は愕然としました。育児との両立が厳しいことを伝えても、一切耳を貸さない。
長年フロアリーダーを務めている僕は会社にとっても中堅格以上の人材であるはずで、会社にとって辞めさせるメリットはないと思われます。
「男性育休を取るような君は、もう辞めてもらって構わない」と言われているように感じました。状況としては、実際そうですしね…。
「去年ガンになったから、もとからやめさせたかったのか?」「男性育休を取得するのが気に食わないから嫌がらせしてるのか??」色々な考えが頭に浮かび、胸の奥がぐらぐらと煮えたぎるような怒りを覚えました。あの感情は忘れれないと思います。
ちなみに僕はケアマネージャーの資格も持っている為、ケアマネの部署へ異動ではどうか?とも伝えましたが「追加のケアマネは要らないし、考える必要もない」と言われました。
労働局へ相談した結果

このままでは納得できず、次の日すぐに労働局の相談窓口へ行きました。(私の座右の銘は「速攻で即行動」笑)
担当者からは次のような説明を受けました。
育休後の異動自体は法律違反ではない。しかし片道2時間という勤務地に異動させること、それについて本人が「育児が困難になる」と訴えているのを無視することは「育児休業法」に違反する。施設に対して指導を行うこともできる。
この言葉を聞いたとき、一筋の希望が見えました。「法律が味方してくれる」と思ったのです。
上司からの脅し

ところが、事態はさらに悪化します。
労働局に相談に行ったことを直属の上司に伝えたところ、こう言われました。
「労働局が介入したら、お前の嫁が居づらくなるだけだぞ」
僕の妻は同じ介護施設で介護士として働いています。現在は出産の為、産休・育休中ですが、復帰もする予定です。
つまり、僕が施設の対応に異議を唱えれば、妻に嫌がらせをするぞと言っているようなものです。(同じ介護施設内で夫婦二人の育休は、とても迷惑になると思っていた為、異動自体に関しては本当に不満はありませんでした。片道2時間の勤務地でなければですが。)
正直、耳を疑いました。もちろん、労働局が介入することで、僕自身が嫌がらせを受けたり、かなり気まずくなるのは重々覚悟していました。ですが妻を人質のように扱ってくるなんて…。
その言葉を聞きながら僕は「遠方へ異動or退職しか道が残されていない」絶望を感じていました。
退職を決意

退職を決意した怒りポイント
今回の男性育休に対する会社の対応で、僕が特に強い怒りを感じたのは
- 最初は表面上良い反応を示しておきながら、後から異動を宣告してきたこと
- 異動の撤回を求めても「個別の事情は聞かない」と突っぱねられたこと
- 労働局に相談したことを告げると「嫁が居づらくなる」と脅されたこと
最初から「前例がないので調整が必要」と言ってくれれば、取得日数を短くしたり他の方法を考えることもできました。妻を脅しの材料に使ってくることも人として、絶対に許せないと思いました。
まぁ多分、男性育休を申請した時点で、会社側としては見切りをつけた感じかもしれませんが…。
家族を守る為の判断
ありのままを労働局に伝えて介入してもらったとしても、現実的には改善を促されるだけで終わる可能性が高い。「異動はやめてあげなさい」程度の介入で、僕と妻、そして生まれたばかりの子どもの生活を根本から守ってくれるわけではない。
だったら、波風を立てずに自分が身を引くしかないと考えるようになりました。つまり施設の対応に文句は何一つ言わず退職するという決意をしました。
これは僕のポリシーにはかなり反していて、ものすごい葛藤がありました。「間違っていると思ったら間違っていると言う」それでどれだけ嫌われようとも、どんな目にあおうとも。僕はそれの方が大切だと信じて33年間生きてきています。
ただ、今回は家族の生活・妻の働きたいという意向を優先するべきだと思いました。
「4ヶ月の育休を取った後、異動なら退職して、家の近くの介護施設に再就職する」
「妻は今の施設に残り、産休・育休後に時短勤務で復帰する」
現状ではこれが家族の生活を守る為に最善の道だと思っています。
男性育休のメリット・アドバイス

男性育休のメリット
ここまで男性育休のデメリットばかりを紹介している為「男性育休=ネガティブな体験」と思われたかもしれませんが、実際には大きなメリットもありました。
- 赤ちゃんと一緒に過ごすかけがえのない時間が得られた
- ミルク・寝かしつけ・おむつ替え等を妻と協力して行い、夫婦の絆が深まった
- 父親としての自覚や家事・育児のスキルが格段に上がった
- 一旦仕事を離れてみる事で、家族というコミュニティの大切さを再認識できた
これらは男性育休を取らなければ絶対に得られなかった経験です。
【関連記事】
これから男性育休を考えるパパへ
最後に、これから男性育休を考えているパパたちへのアドバイスをまとめます。
- まずは会社の過去の男性育休取得のパターンを確認すること
⇒男性育休を取得したことのある先輩に聞くのが一番良いですね。 - 上司や人事とのやり取りは記録に残すこと
⇒何かあった時、記録やメールでのやり取りは後々の証拠となります。 - 妻とよく話し合うこと
⇒夫婦で「何を大事にするか」を共有しておけば、会社に対して毅然とした対応を取れます。 - 最悪のケースを想定しておくこと
⇒僕のように退職に追い込まれたとしても、生活していける選択肢も考えておきましょう。
男性育休を調べていると、嫌味や圧力、昇給・昇進の機会を無くされたりと色々なパターンの嫌がらせがあるようですね…。
もし不利益な扱いを受けた場合、労働局などの相談先もあります。実際に動いてもらうかはともかく、相談できる場所があるというのは覚えておいてくださいね。
まとめ
僕は現在4ヶ月間の男性育休を取得中です。子どもや妻と過ごせている今の時間は一生の宝物になるでしょう。しかしその裏で、理不尽な異動宣告といった厳しい現実にも直面しました。
男性育休は、まだまだ社会の中で浸透しきっていません。理解ある職場もあれば、僕のように理不尽な対応を受ける人もいるかもしれません。それでも、僕は声を大にして言いたいです。
「子どもと過ごす時間は、どんなキャリアや肩書きよりも価値がある」
仕事も大事ですが、子どもと過ごせる時間は本当に一瞬です。自分と家族にとって一番良いと思える選択をしてください。
これから男性育休を考えるパパたちが、首尾よく仕事と子育ての両立をして、家族との時間を大切にできることを心から願っています。
最後までご覧頂きありがとうございました。
【次のおススメ記事】


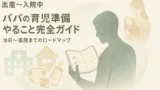


コメント