こんにちわ。今年から新米パパデビューしたたまいちです。
僕は自信過剰な男でして、出産前は「家事もそれなりにできるし、子育て問題なく出来るだろう」と思っていました。
でも実際に妻の出産後1ヶ月を過ごしてみると、想像と現実には大きなギャップが…。
夜泣き対応や家事全般を担う中で、「できる」と「実際にやる」の違いを痛感し、思うように自分の時間を持てないもどかしさに直面…。
ただ一方で、赤ちゃんの新しい表情や成長の瞬間に立ち会えたことで、大きな喜びも感じています。
この記事では、新米パパとして1ヶ月間過ごした体験から学んだことについて紹介していきます。
これから新米パパになる方が少しでも準備万端、前向きな気持ちで家事や子育てに向き合えるような内容をお伝えできたらなと思います。
出産後1ヶ月のリアルな家事と子育て体験
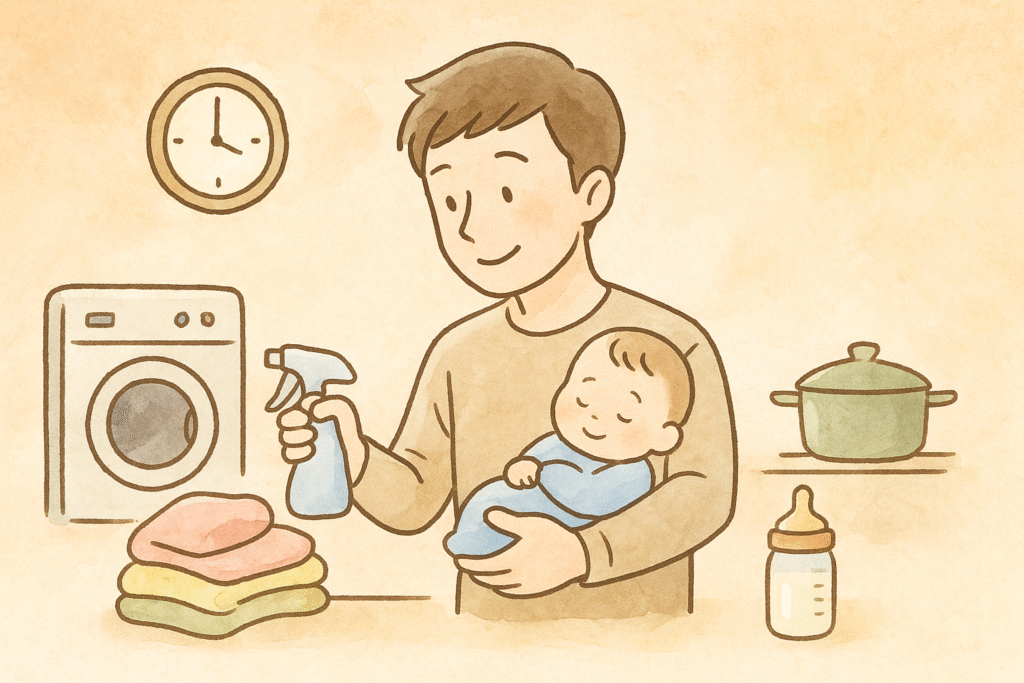
家事の「できる」と「やる」の違いを痛感
独身だった時は料理も洗濯も掃除も全て自分で行っていた為「家事はやろうと思えばいつでもできる」と思っていたんです。
でも実際には、出産後の妻の体調が優れない中で、毎日すべての家事を自分一人で回すことになって、考えていた以上の大変さを味わいました。
「できる」と「やる」はまったく違う。これが最初の大きな気づきです。
疲れていても休めない。子どものタイミングに左右されて予定通りに進まない。想像していた子供が産まれた後の家事と現実に行っている子供が産まれた後の家事は本当に全く違うものでした。
これから新米パパになる人には、妻の出産後になったら「できる」と思っていることを、まずは出産前から実際にやってみてほしいと思います。そこで全く出来ないのであれば、奥さんに徹底的に教えてもらいましょう。
出産後で体調不良・ホルモンバランスが乱れている奥さんに「砂糖ってどこにあるんだっけ?洗濯機って使い方これでいいの?」なんて聞いていられませんからね…。
夜泣き対応で見えた新米パパの限界と工夫
出産前は「夜泣きで起きるのは大変そうだけど、頑張ればなんとかなる」と思っていました。
でも実際に赤ちゃんが生まれてみると、3時間おきにミルクをあげる生活に。
1回の対応には、ミルクを作る・あげる・ゲップをさせる・寝かしつける…と、だいたい30〜50分かかります。
そうなると自分が眠れる時間は1時間半〜2時間程度しかなく「眠れたようで眠れていない」状態が積み重なるのは想像以上にしんどかったです。
そこで工夫したのが、ミルクは1回ごとの交代制です。
「1回は僕、次は妻」というように交互に対応することで、どちらかはまとまって眠れる時間を確保できるようにしました。
結果的に、大体夜20時から朝8時の間に、それぞれ5時間ずつは睡眠を取れる体制を整えられました。
もちろん交代制でも完全に疲れが取れるわけではありません。
でも「次は相手が対応してくれる」と思えるだけで気持ちが軽くなり、夜泣きに向き合う余裕が生まれます。
この経験から伝えたいのは、夜泣き対応は二人で工夫して“休める時間を確保すること”が大切だということです。
夫婦で育休を取ったからできた協力体制
出産前から「夫婦で協力するのが大事」という意識はお互いにありましたが、実際にやってみるとその“協力”の中身は想像以上に複雑でした。
授乳やオムツ替えだけでなく、洗濯や掃除、買い物など日常のすべてが赤ちゃん中心に回るので、夫婦が全てをどう分担出来るかで体力も気持ちの余裕も大きく変わります。
僕の家の場合、幸いなことに夫婦ともに育休を取得できたので、昼も夜も二人で赤ちゃんを見られる体制を整えられました。これは本当に大きなポイントだったと思います。
夜の対応では「1回ごとに交代制」にすることでお互いにまとまった睡眠を確保できましたし、昼間でも「今日は僕が家事メイン、妻が赤ちゃんのお世話メイン」と役割を分けたり、「妻が昼寝している間は僕が赤ちゃんを見る」といった調整ができたのも、二人で育休を取っていたからこそ可能だったことです。
この育休生活をしてみて強く感じたのは、【二人で赤ちゃんを育てる】という意識を持てるかどうかで、産後の夫婦関係も大きく変わるということ。
どちらか一方が無理をすると、その負担は必ず相手にも返ってきます。産後の恨みは一生とよく言いますが、それほど大変な時期であるという事を実感しました。
だからこそ、役割分担を柔軟に変えながら「二人でやっていく」体制を作れたのは、本当に良かったと感じています。
新米パパとして意識した夫婦の役割分担
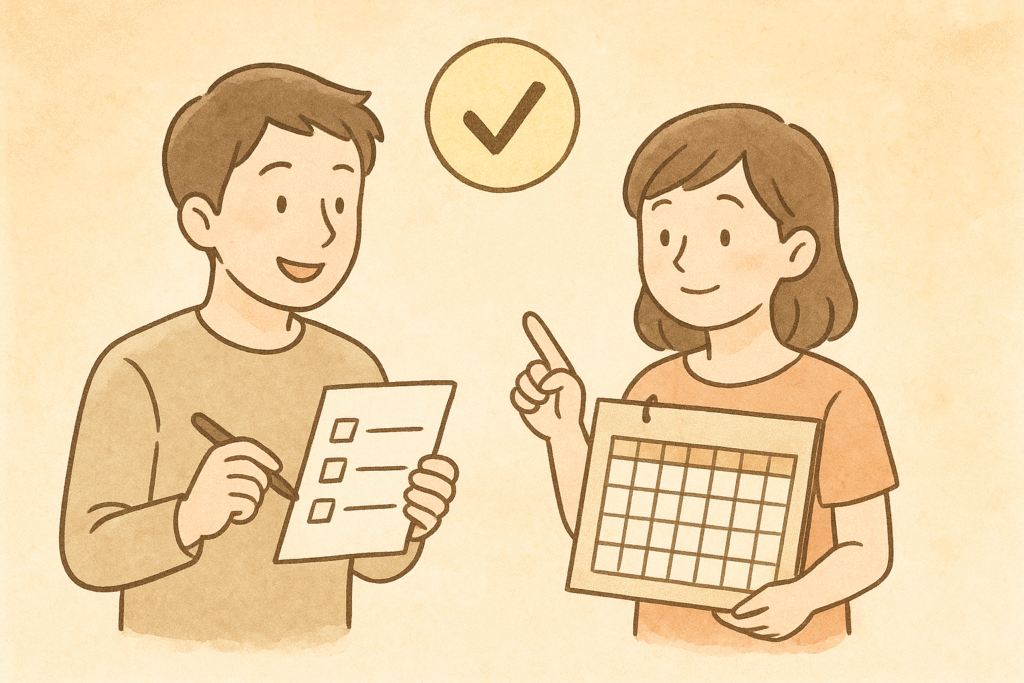
産後1ヶ月は妻を休ませることを最優先に
僕たち夫婦は出産前からある程度、家事や育児の役割分担を決めていました。
でも実際に赤ちゃんが生まれてからは、その<分担>の内容を改めて考えさせられました。
妻は出産後の体調があまり良くなく、子どものことをするのも精一杯という様子でした。体調が良さそうと妻自身が言って動いてくれる日もありましたが、出産のダメージから回復出来ているわけではありません。
そこから意識したのは、産後1ヶ月は妻をできるだけ休ませること。
だから「妻ができると言ったことは任せる」ではなく、僕ができることはすべて僕がやるという姿勢で動くようにしました。
ここで、先ほどもお伝えしましたが、特に家事は「できる」と「実際に全部やる」には大きなギャップがあります。
料理・洗濯・掃除を一人で担うのは思った以上に大変でした。
それでも僕が動くことで、妻が横になれる時間や睡眠を確保できるなら、妻が休めた分だけ家庭の雰囲気も良くなるので、それが一番大きなメリットだと感じました。
また、役割や完璧を意識しすぎずに柔軟に変えることも大切だと思います。
例えば子供の世話が大変と妻が強く感じているなら、出来る範囲の家事を妻にやってもらって子供の世話はパパがしたり、家事がなかなか進まない日があったら育児に専念して家事は後日に回したりと、とその日その日の状況に応じて行動を変える必要があり、役割分担は<平等>より<最適>を意識することが必要なんだと学びました。
「どちらがどれだけやったか」や「これができてないあれができてない」なんてことを気にするより「今日は相手が楽になれる分担かどうか」を考えながら行動する方が、夫婦関係もずっと良い方向に進むと感じました。
時間管理の難しさと自分のリズム喪失
出産前は「赤ちゃん中心の生活になる」とわかっていたつもりでしたが、実際に過ごしてみると想像以上に自分の時間はなくなりました。
朝7時に1日がスタートすると、洗濯・ミルク・食事作り・洗い物…と気づけば次の授乳時間。午前中の家事を終えたころにはもう昼が近く、昼食を作って片づけをしているとあっという間に午後に突入します。買い物や夕食の準備、沐浴や寝かしつけをこなしていると、気づけば夜。ようやく「自由時間」と呼べるのは20時半から21時頃ですが、それも次の授乳までのわずかな時間だけでした。
夜も3時間おきにミルク対応があり、まとまった睡眠はほとんど取れません。昼寝で補おうとするとさらに時間は削られてしまいます。結果的に、趣味やリフレッシュのための時間はほぼゼロ。頭では覚悟していたつもりでも、実際に「自分のリズムが完全になくなる」ことは大きなストレスでした。
少しの期間ですが、一人で全てを行ってみてワンオペ育児の大変さを理解できましたね…。
「まとまった自由時間を確保すること」の難しさを知った為、妻の体調が回復してからはお互いに自由な隙間時間を作るようにしました。
ミルクの交代などのタイミングで好きなコーヒーを淹れて少しゆっくりしたりと、ほんの少しでもお互いに好きなことを行える時間を作ることで、少しだけ心に余裕が生まれた気がします。
新米パパが感じた家事と子育ての学び
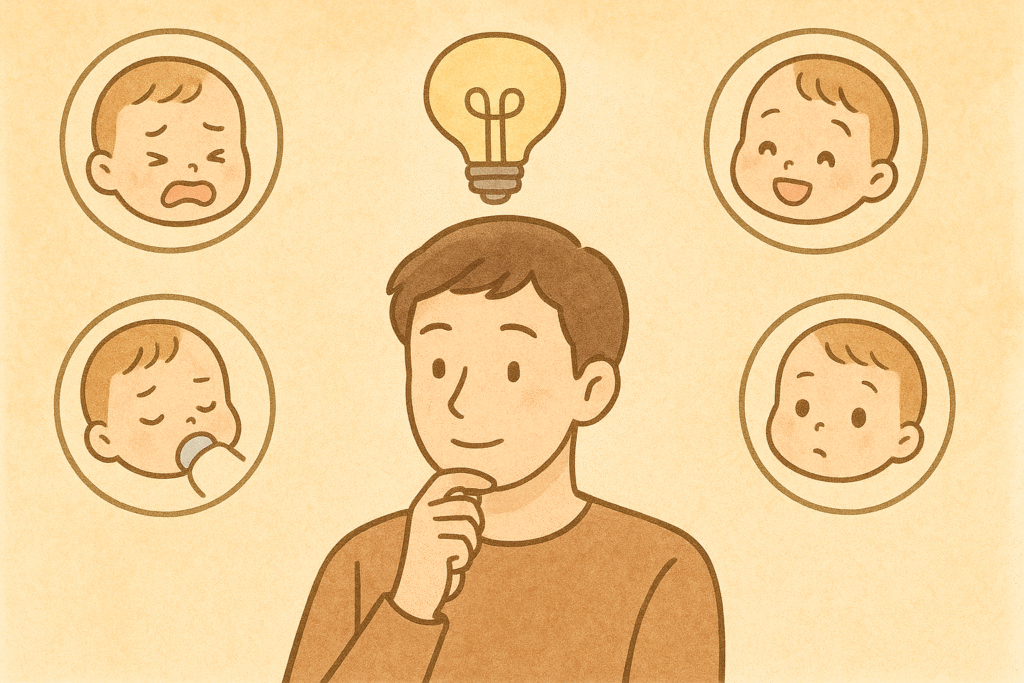
家事は「完璧」より「継続」が大事
産後1ヶ月を振り返って強く思ったのは、家事は「完璧にやろうとする」よりも「無理なく続けられる形を作る」ことのほうが大切だということです。最初は自分で全部やらなければと意気込んでいましたが、結局それでは疲れ切ってしまいます。臨機応変に交代できる環境、食洗機や宅配サービスなど【人やモノに頼る工夫】をもっと早くから取り入れていれば、もう少し余裕を持てたと感じました。
赤ちゃんの成長が与えてくれる喜び
育児はとても大変ですが、赤ちゃんの小さな変化に心が救われる瞬間も多々あります。寝顔の安らぎ、目が合ったときの笑み、手をぎゅっと握ってくれた感触、その一つ一つが「大変だけど頑張ってよかった」と思わせてくれます。
特に産後1ヶ月は不安や疲労が重なる時期ですが、赤ちゃんの成長を感じる瞬間も多い時期ですので育児に参加できてよかったと思っています。
「自分のリズムは崩れる」と最初から受け入れる
そして何より学んだのは「出産前の生活リズムを維持するのは不可能」だということです。睡眠も食事も、自分のペースは完全に崩れます。最初はその変化に戸惑いましたが「崩れるのが普通」と受け入れたことで、気持ちがかなりラクになりました。
そのうえで、短い隙間時間をどう活用するかを考えるほうが現実的ですし、気持ち的にも前向きになれて余裕も生まれます。
まとめ(新米パパが伝えたいこと)
出産前は育児に対して「夜泣きは大変そう」「家事も自分がやればなんとかなる」と、どこか軽く考えていました。けれど実際に妻の出産後1ヶ月を過ごしてみると、想像以上に自分の時間はなく、生活リズムも崩れ、体力的にも精神的にも限界を感じる瞬間が何度もありました。
ただ同時に、夫婦で協力することの大切さや、家事は「完璧」より「継続性」が大事だという学び、そして赤ちゃんの成長が与えてくれるかけがえのない喜びを実感できました。
これから新米パパになる人に伝えたいのは
「妻に全部を一人で背負わせない」「自分も全部を一人で背負わなくていい」ということ。
育児も家事も、夫婦で試行錯誤しながら<その家庭に合った形>を見つけていけば大丈夫ですし、大変な日々の中にも必ず「喜びや幸せを感じる瞬間」があるあります。
そんな瞬間を思い浮かべながら楽しんで育児に参加して欲しいです。
僕の経験が、これから始まる新米パパの育児生活に少しでも役立てば嬉しいです。
最後まで閲覧頂きありがとうございました。
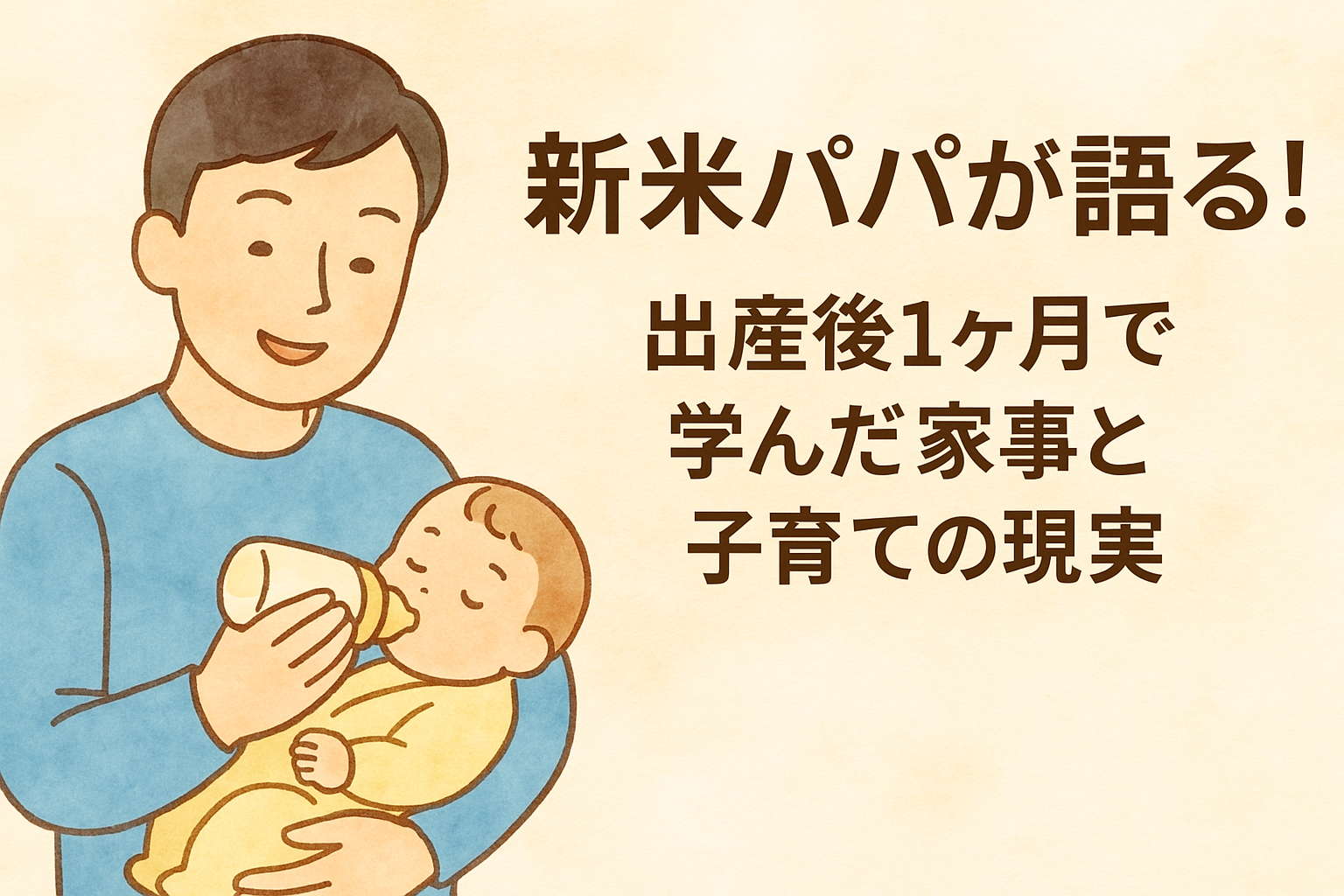


コメント